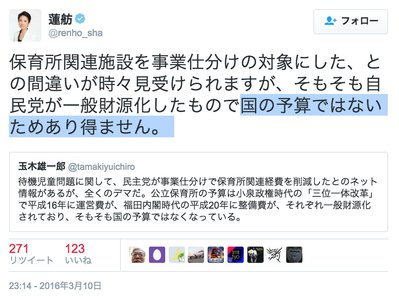1: 6564億円◆o8vqQW81IE 投稿日:2016/02/06(土)23:12:25
7: 6564億円◆o8vqQW81IE 投稿日:2016/02/06(土)23:30:31
>>1
【NHK】NHKの韓国語アナウンサーが沢山いる件。[5/21]
/r/open2ch.net/newsplus/1400667626/in
9: へんくつ者 投稿日:2016/02/07(日)00:00:39
>>1
ぎぇーーーーーーっ。なんだNHK。解体解体、大リストラ!!!!
17: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)01:28:10
>>1
本当に反吐が出る
解体しかない
18: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)01:29:28
>>1
官邸に連絡。
嘘はいかんよ、嘘は。
29: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)05:38:59
34: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)07:33:07
>>1
NHKはJAPANデビューの件で懲りたのかとおもったら
まーだそんな雑なことをしているんだwww
35: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)07:35:00
特に南京城内に限定していえば、おおまかな状況からして>>1の説明に反する
教育番組でそれをやるようでは解体かな
47: 6564億円◆o8vqQW81IE 投稿日:2016/02/07(日)11:06:00
>>1
皆さん、こんにちはm(__)m
以下のスレは、395レス頂きました「通州事件」に関するスレです。
初めての方、興味のある方は、是非ご覧ください。
なお、残虐性のある表記がありますので、苦手な方は見ない方がよいです。
【ねずさんのひとりごと】(支那人の残虐性)通州事件の惨劇「Sさんの体験談」※この記事は18禁です。18歳未満の方と女性の方はお読みにならないでください。[H27/7/30]
/r/open2ch.net/newsplus/1438196122/l50
2: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/06(土)23:14:27
今って教科書には載っているんだろうか?
3: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/06(土)23:18:24
>日本史監修:創価大学教授 季武 嘉也
コイツのせいか?
11: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)00:26:19
>>3
氏、キムって読むのか?
15: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)01:09:50
4: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/06(土)23:21:18
5: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/06(土)23:23:04
6: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/06(土)23:26:16
もう真面目に解体を考えてもいいと思う
あとこれどこの教科書を参考にしてるんかな
8: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/06(土)23:31:07
労働力確保のため地域の人間を
無意味に虐殺する必要などないのですよw
民族大虐殺を繰り返してきた
特定アジアの思想と一緒にしないでほしいものだ
10: 埼玉のサラリーマン◆sfVujU9KsLCf 投稿日:2016/02/07(日)00:14:30
あー。絶対契約しないわ。
理由がもう一つ増えた。
放送法4条を守らないのに、64条だけ守れってのは筋が通らねえぜ。NHKさんよぉ。
12: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)00:48:37
抗日戦8年半の間に中国で3500万人の犠牲者が出た筈なのに何故南京しか文句言わないんだろう
ふしぎだなー
13: ■忍法帖【Lv=5,そうりょ,SC4】 投稿日:2016/02/07(日)01:02:22
何を根拠にしているんでしょうね?
14: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)01:08:50
>>13
∧_∧
(-@∀@) 根拠とか、必要ですか?
_φ 朝⊂)
/旦/三/./|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| |/
16: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)01:18:07
日本人を舐めてるんだ
19: FX-502P 投稿日:2016/02/07(日)01:34:45
解体だ
矯正は無理
関わった人間も処分せよ
20: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)01:37:36
政府見解とは異なるのだから、番組関係者は更迭だな。
NHKは再発防止策を発表して、公正中立な番組制作に邁進するよう、総務省から指導せよ。
21: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)02:03:44
日本史でもしっかりと文化大革命について勉強させればいい
22: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)02:08:06
言い逃れできないように連座適用にしなきゃ駄目だよ
23: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)02:16:23
通州事件は触れないの?
日本の女、子供が中国軍に虐殺された事件。日中戦争の原因の1つ
24: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)02:23:36
通州事件に触れる前に尼港事件だな。
日本人が共産党を敵視する原点ともいうべき虐殺事件。
済南事件も含めた三つの日本人虐殺事件を取り扱ってこそ、公正中立。
25: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)02:23:55
虐殺という言葉を用いるならば通州事件こそが適切
26: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)02:30:04
日本国民の金で反日活動するキチガイ放送局
27: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)05:02:47
何年か前にNHKで放送された朝鮮半島の歴史もなかなか香ばしい感じだったけどね
あんまり覚えてはないけど日本で教わるのとは違う感じだったよ
28: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)05:24:06
予備知識のない子供の脳に入る誤った情報は、なかなか消えんぞ
30: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)05:57:39
こんなことされるとなんか気楽にへらへら笑いながら機材以外殲滅とかできちゃうよ~ ニコニコ
31: ブヒったー 投稿日:2016/02/07(日)06:19:07
報道の自由は必要なんだろうが、
報道の責任も併せて論じてくれないと困るわな
精度の低い情報を拡散したマスゴミに対して、
何らかの罰は必要だっての
33: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)07:30:38
犬HKの歴史歪曲がひどい
36: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)07:38:33
史家同士が「南京の話でもする?」と言って議論なり対談を始めたら通常は南京城壁内をさす
なのに、南京で大虐殺がおこなわれたとする人々は、南京城内外の話を混ぜる
そこらへんも傍観者を混乱させるもとだ
他にも色々ある
東京新聞なんか読んでるとまるでプロパガンダ紙
あ、「まるで」は要らないか
41: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)09:41:26
>>36
しかも城外の被害は清野作戦と言って、国民党軍が焼き討ちした被害で、帝国陸軍は無関係www
城内へ入ってからは憲兵が徹底的に非戦闘区域への攻撃を抑止力したので、駐在してた各国記者が絶賛している。
しかも南京虐殺事件て、発生したと言われている時点から八年以上も経過して出て来た。
中国人の性格から考えて、八年も黙っているなんて無理w
43: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)10:17:57
>>41
人口に関する指摘も色々とおかしい
南京城壁が崩されたのは日本軍が入城した数年後の話なので、あっちの主張は物理的にもありえず支離滅裂
46: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)10:53:14
>>43
世界中の数学者を集めて、
>>20-30=25
の謎を解明して貰おうぜwww
39: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)08:41:26
【政治】NHK予算案がピンチ! 自民総務会が不祥事理由に再び了承せず H28/2/2
/r/open2ch.net/newsplus/1454420888/
>産経新聞の写真には、総務会に臨んだ茂木選対委員長、高村副総裁、二階総務会長、谷垣幹事長、稲田政調会長が
写っている。
この辺にチクればいいわけね
40: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)08:43:58
こないだ自宅で危険ドラッグ製造(!!)してた局員が捕まってたけど
もしかして局内に蔓延してるんじゃないの
42: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)10:15:22
日清戦争や日露戦争、義和団の乱とか日本の兵隊は紳士的なのに
第2次世界大戦になると女子供を殺す蛮族になるんだよね
44: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)10:20:15
併合して民度が下がったのか、極東の憲兵はどこに行ったんだろうな?
45: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)10:49:37
総務相って、犬HKから賄賂貰うだけの省庁なのか・
こんな無駄な省庁は、さっさと潰せ、
厚労省も、外務省も財務省も何もいらない。
全部はじめから作り直して、公務員は退職したら、天下りできないようにやがれ。
それと各省庁の公務員は、出世できないようにしろ。
出世できない奴を、関係団体に天下りさせるから、変な利権ができるんだ。
始めから終わりまで、全期間平の公務員にして、これまで次官とかやってたのは、単なる配置にして、役職にするな。
48: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)12:01:11
通州事件にふれず、南京のことだけに触れるNHKってorz
54: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)13:00:43
>>48
インキン事件の虚構を覆す本当の虐殺事件だからな
教育現場においてもインキン事件ばかり扱ってきたのも頷ける
55: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)13:02:12
>>54
かぼちゃに対する熱い風評被害が出そうな言い換え
49: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)12:03:43
通州事件ってびっくりするくらい知名度低いからな
ユネスコ登録するって動きをしてる団体があるんだけど
登録で着るできないに関わらず、運動が拡散活動になるんでがんばって欲しい
50: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)12:20:05
このスレかな
【国際】「通州事件」ユネスコ記憶遺産に申請へ つくる会「世界に知ってほしい」 中国軍の邦人200人殺害 [H27/12/12]
/r/open2ch.net/newsplus/1449849237/
51: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)12:23:39
>>50
お、それやw
52: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)12:25:46
通州事件だけじゃ無いしね
一連のが広まれば軍部の暴走なんて事も言えなくなるからアカとしては都合が悪いんだろ
53: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)12:58:43
モミーを恫喝してたシナ猛はこれを追及してみろ
報道が萎縮するからできませんってか?
56: ?エラ通信■忍法帖【Lv=21,あやしいかげ,BOn】 投稿日:2016/02/07(日)13:02:20
ちなみに、Nhkも最高裁もおなじぐらい、日本国民の敵
57: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)13:02:35
暴走つうより迷走だよなあれ
リーダーに権限の無いシステムと
暴力均衡のシビリアンコントロール不在なんは戦前日本の宿阿
>>1927年日本大使館襲撃表記しろや
上下関係しか無いあの国は相手を舐めだしたら調子のるんだから
59: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)13:55:16
>>57
立憲政友会と立憲民政党の二大政党で、選挙の度に政権交替が起きていたんだから、仕方ないだろw
互いに足の引っ張り合いをした挙げ句の果てに、政友会犬養毅が「統帥権の干犯問題」を言い出して、軍部独走の下地を作った。
いつの時代も、目先の小利を追いかけては失敗するのが通例。
58: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/07(日)13:04:40
結局アジア主義者は戦前も戦後も日本のガン細胞
引用元: 【NHK】NHK教育 高校講座「日本史」~「女性や子どもを含む多くの中国人を殺害」字幕付きで放送 [H28/2/6]